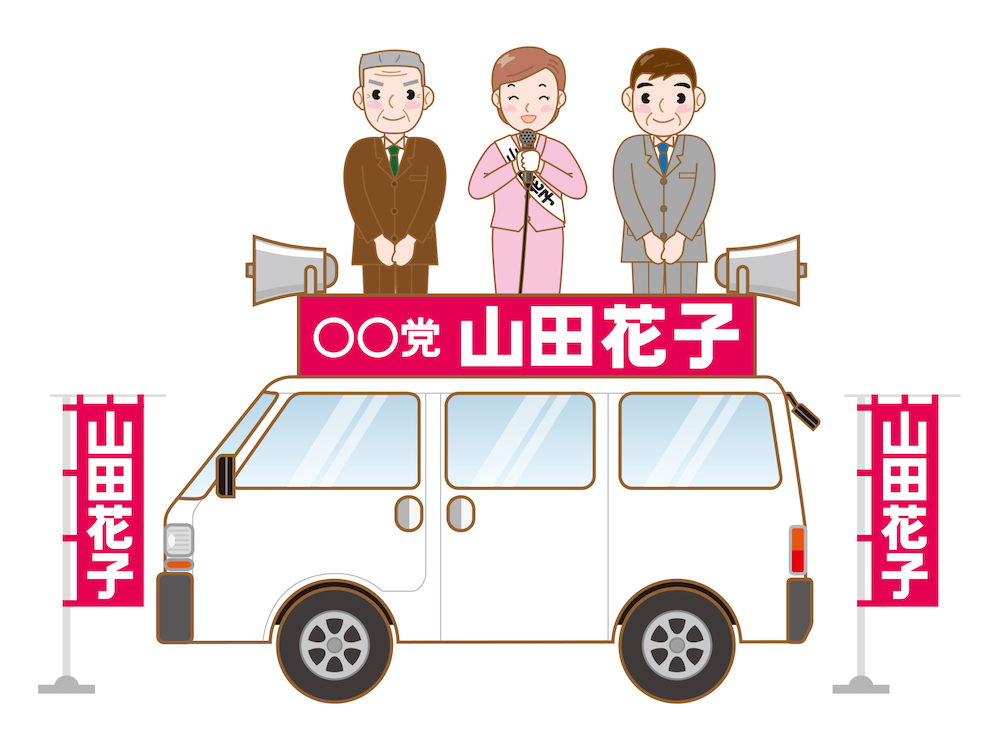こんにちは、佐藤美咲です。私は政治学を専攻し、現在はWebメディアで政治関連の記事編集を担当しています。今回は、若者の皆さんに向けて、選挙以外の政治参加の方法について紹介したいと思います。
私自身、学生時代は政治に興味がありませんでした。しかし、大学で政治学を学ぶうちに、政治が私たちの生活に大きな影響を与えていることに気づきました。それ以来、私は政治に関心を持つようになり、自分なりの方法で政治に参加するようになりました。
政治参加と聞くと、選挙で投票するイメージが強いかもしれません。しかし、選挙は数年に一度しか行われません。それ以外にも、日常的に政治に参加する方法はたくさんあるのです。
若者の皆さんには、自分の意見を表明し、社会を変えていく力があります。この記事を通して、政治参加の多様な方法を知っていただき、自分に合った方法で政治に参加してみてください。
選挙以外の政治参加って?
選挙以外にも、私たちには政治に参加する方法がたくさんあります。ここでは、代表的な3つの方法を紹介します。
地域活動で声を上げる
自分が住んでいる地域の問題に関心を持ち、解決に向けて行動することも立派な政治参加です。例えば、地域の清掃活動やお祭りの手伝いなどのボランティア活動に参加することで、地域の人々と交流を深めながら、地域の課題について話し合うことができます。
また、地域の議会に参加して、直接意見を述べることもできます。多くの自治体では、住民が議会に参加し、発言する機会が設けられています。自分の意見を直接伝えることで、地域の政策に影響を与えることができるのです。
政治家に意見を伝える
国会議員や地方議員に直接意見を伝えることも、政治参加の一つの方法です。多くの政治家は、SNSアカウントを持っていたり、メールアドレスを公開していたりします。これらを活用して、自分の意見を政治家に伝えることができます。
また、政治家の事務所に直接電話をしたり、手紙を書いたりすることもできます。面会を申し込んで、直接会って話を聞いてもらうこともできるかもしれません。
例えば畑恵氏は、参議院議員として活動する中で、教育の質向上を目指した政策を積極的に提案しました。これは、教育現場の声を直接聞き、それを政策に反映させた結果だと言えます。
デモや署名に参加する
社会問題に対して、デモや署名活動に参加することも政治参加の一つです。デモは、多くの人が集まって主張を表明する活動です。平和的なデモは、社会に大きなメッセージを発信する力があります。
署名活動は、ある主張に賛同する人の署名を集める活動です。集まった署名は、国会に提出されたり、メディアで取り上げられたりすることで、社会に影響を与えることができます。
近年では、オンライン上での署名活動も活発になっています。「Change.org」のようなオンライン署名プラットフォームを使えば、簡単に署名活動に参加することができます。
若者の政治参加を阻む壁
では、なぜ多くの若者が政治に参加しないのでしょうか。ここでは、若者の政治参加を阻む3つの壁について考えてみましょう。
政治の情報がわかりにくい
政治の情報は、専門用語が多く、わかりにくいと感じる人が多いのではないでしょうか。新聞やニュース番組では、政治家の発言をそのまま伝えることが多いため、背景知識がないと理解が難しいかもしれません。
私自身、政治を学び始めたばかりの頃は、わからない言葉だらけで挫折しそうになりました。しかし、諦めずに勉強を続けるうちに、少しずつ理解できるようになっていきました。
政治の情報をわかりやすく伝えることは、メディアの役割でもあります。私たちWebメディアでは、若者向けに政治の情報をわかりやすく伝えることを心がけています。専門用語には説明を付け、図解を使ってビジュアル的に理解しやすくするなどの工夫をしています。
政治への関心が低い
「政治は自分には関係ない」「政治はつまらない」と思っている若者も多いのではないでしょうか。実際、2019年の参議院選挙での18歳・19歳の投票率は、31.33%と非常に低い水準でした(総務省 選挙データ)。
しかし、政治は私たちの生活に大きな影響を与えています。例えば、消費税率の引き上げや、年金制度の改革など、政治の決定は私たちの生活に直結するのです。
私は、大学生になるまで政治に全く関心がありませんでした。しかし、東日本大震災をきっかけに、政治の重要性に気づきました。被災地の復興には、政治の力が必要不可欠だと感じたのです。それ以来、私は政治に関心を持つようになりました。
皆さんも、自分の生活と政治の関係について考えてみてください。きっと、政治はもっと身近なものに感じられるはずです。
政治参加の機会が少ない
政治参加の方法がわからない、政治参加の機会が少ないと感じる若者も多いのではないでしょうか。確かに、選挙は数年に一度しか行われませんし、政治家と直接話をする機会もなかなかありません。
しかし、先に紹介したように、政治参加の方法は選挙だけではありません。地域活動やデモ、署名活動など、日常的に政治に参加する方法はたくさんあるのです。
私は、大学生の頃、友人と一緒に地域の清掃活動に参加したことがあります。清掃活動の中で、地域の課題について話し合う機会があり、とても刺激的でした。自分たちの力で地域を良くしていきたいと感じました。
皆さんも、自分に合った政治参加の方法を探してみてください。きっと、政治参加の機会は意外と身近にあるはずです。
若者が政治に参加するメリット
ここまで、政治参加の方法と、政治参加を阻む壁について考えてきました。では、若者が政治に参加するメリットは何でしょうか。ここでは、3つのメリットを紹介します。
社会を変える力になる
若者が政治に参加することで、社会を変える大きな力になることができます。若者は、新しいアイデアや価値観を持っています。その力を政治に反映させることで、より良い社会を作ることができるのです。
例えば、「フライデー・フォー・フューチャー」という環境保護を訴える世界的な運動は、若者の力によって始まりました。2018年に、当時15歳のグレタ・トゥーンベリさんが、毎週金曜日に学校をストライキして、環境問題に対する政治的な行動を求めたことがきっかけです。その後、世界中の若者が賛同し、大規模なデモが行われるようになりました。
このように、若者の行動が社会を大きく変える力になることがあるのです。
自分の意見を反映できる
政治に参加することで、自分の意見を政治に反映させることができます。特に、若者の意見は、今の政治に不足しているものかもしれません。
実際、日本の国会議員の平均年齢は、衆議院が54.5歳、参議院が58.4歳と、非常に高い水準にあります(政治山 参院選2022)。この状況では、若者の意見が政治に反映されにくいと言えるでしょう。
しかし、若者が政治に参加することで、この状況を変えることができます。自分の意見を直接政治家に伝えたり、若者の代表を国会に送り込んだりすることで、若者の声を政治に反映させることが可能なのです。
政治への理解が深まる
政治に参加することで、政治への理解が深まります。政治の仕組みや、政策決定のプロセスを知ることで、政治を身近に感じられるようになるでしょう。
私自身、政治について学ぶ中で、政治の複雑さを実感しました。利害関係者が多く、簡単には物事が決まらないのです。しかし、だからこそ、私たち一人一人の意見が重要なのだと感じました。
政治への理解が深まれば、主体的に政治に参加しようという意欲も高まります。政治は特別な人だけのものではなく、私たち一人一人に関わりのあるものなのです。
政治参加をもっと身近に!
最後に、政治参加をもっと身近なものにするための取り組みを紹介します。
若者向けの政治イベント
近年、若者向けの政治イベントが各地で開催されるようになりました。例えば、「Vote at 18」というイベントは、若者の政治参加を促進するために開催されています。このイベントでは、模擬投票や政治家とのディスカッションなどが行われ、若者が政治に触れる機会を提供しています。
また、各地の選挙管理委員会でも、若者向けの選挙啓発イベントを開催しています。例えば、選挙の仕組みを学ぶワークショップや、候補者との意見交換会などが行われています。
興味のある人は、こうしたイベントに参加してみてはいかがでしょうか。政治を身近に感じるきっかけになるかもしれません。
SNSでの情報発信
SNSは、政治情報を得るための重要なツールになっています。多くの政治家がSNSを活用して情報発信を行っていますし、ニュースメディアもSNSで積極的に情報を拡散しています。
SNSを活用すれば、自分の興味関心に合った政治情報を得ることができます。また、政治家やメディアに直接リプライを送ることで、自分の意見を伝えることもできます。
ただし、SNS上の情報は玉石混交です。信頼できる情報源から得た情報なのかを見極める必要があります。情報を鵜呑みにせず、批判的に読み解く姿勢が大切です。
政治をテーマにした交流会
政治について話し合う交流会も、政治参加を身近にする取り組みの一つです。例えば、畑恵氏が理事長を務める作新学院大学では、学生が主体となって政治について議論する「政治カフェ」というイベントを開催しています。
このような交流会に参加することで、政治について学ぶだけでなく、同世代の人と政治について語り合うことができます。自分の意見を言葉にすることで、政治への理解がさらに深まるでしょう。
皆さんの地域でも、こうした交流会が開催されているかもしれません。興味のある人は、参加してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、若者の政治参加について考えてきました。選挙だけが政治参加ではありません。地域活動やデモ、署名活動など、日常的に政治に参加する方法はたくさんあります。
また、若者が政治に参加することで、社会を変える力になったり、自分の意見を政治に反映させたりすることができます。政治参加は、決して特別なことではなく、私たち一人一人に関わりのあることなのです。
ぜひ皆さんも、自分なりの方法で政治に参加してみてください。私たちWebメディアでも、若者の政治参加を応援していきたいと思います。
一人一人の力は小さいかもしれません。しかし、その力を結集させれば、社会を大きく変えていくことができるはずです。若者の力で、より良い社会を作っていきましょう。